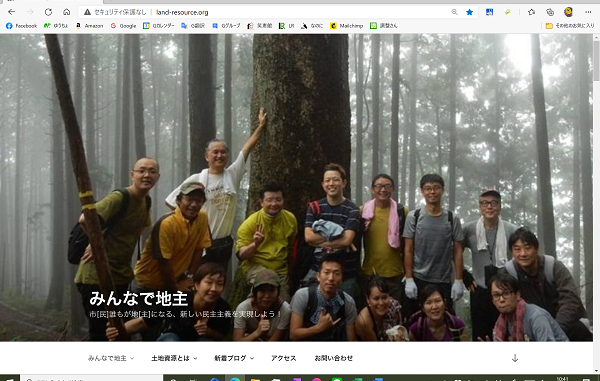
地主は明治維新で廃止され、言葉だけが名残として残っている。
「土地所有」という言葉が、明治維新の前後では全く違う意味なので、「地主≠土地所有者」を説明するのは一苦労だ。
日本では、7世紀ごろには豪族たちが地方を支配するようになり、新たに開墾した者に土地所有権が認められる荘園制度が広がった。
だが、この「認められる」という言葉が権利を示すことを忘れてはならない。
所詮権利とは、支配者が被支配者に与えるもので、昔の所有権とは、「年貢のノルマ」のようなもの。
「所有権」を与える領主は「領有権」に基づいて支配しているが、これは力づくで奪い取り、周囲の承認で成り立つ力だ。
・
年貢を効率よく収奪するには、検地によって領地の収穫量を測る必要があるが、年貢の取り立てを行う地元の豪族などの抵抗にあい、検地は進まなかった。
戦国時代になると、国の領主が目まぐるしく入れ替わり、年貢の徴収も混乱したが、やがて北条早雲のような新興勢力が、それまでの既得権益を打ち壊し、検地を実施するようになった。
そして、急速に領地を拡大した織田信長が検地を促進したことで、これを引き継いだ豊臣秀吉は全国の検地(太閤検地)に乗り出した。
検地とは、農地の面積を計測し、それに見合った年貢を課すことだが、農民出身の秀吉はそれまで土地所有者に課していた年貢を耕作者に課すこととして一元化した。
この時すべての農民が実質的な所有者となったのは、民主化というよりは「民従化」と言えるかもしれない。
・
しかし、耕作者による土地所有制は安泰とは言えなかった。
耕作者の能力には格差があり、収量の格差が貧富を生んだ。
やがて、年貢を納めるために耕作者間で年貢米の貸し借りが行われるようになり、その担保には土地があてられた。
集落ごとに、収量の多い実力者が年貢の取りまとめ役に選ばれるのだが、これが「地主」となった。
借りを返すことができない耕作者は、担保の土地を地主に提供し、自分は小作人として耕作を続ける。
かつての集落は、水などの資源を共同で調達する「自給自足経済の単位」だったので、地主は経済的に自立する地域社会の経営者となっていった。
・
やがてペリーの黒船が現れて、外国からの侵略に対抗する帝国づくりが必要となった。
そのために、明治維新ではそれまでのコメ経済を貨幣経済に変えるため、「年貢=現物納税」を廃止して「地租=貨幣納税」に切り替えて、地主制を廃止して地方自治体(町村)を整備した。
日本社会は物々交換経済から貨幣経済に急速な変化して、それまで価値を生み出す資源だった土地は、一気にそれ自体が換金できる資産になった。
その後、敗戦とともに帝国主義を捨て、日本は民主化の道を歩むことになった。
だが、肝心の国土復興は不動産ビジネスと土地投機に依存して、国民の顧客化(民客化)が進むばかり。
昔の日本は地球の一部=日本列島でできていたが、今の日本は時価総額1,400兆円の不動産と言われている。
・
しかし、国土の6割以上が山林の日本では、その価値の大部分は平地に集中し、さらに都市圏への集中が進んだため、ごく一部の平野にその価値は集中する。
山林や耕作地だけでなく、地方都市までもが経済価値を失い放置や放棄が進んでいる。
最近では都市部でも駅周辺の価値が上がり、郊外の空洞化が進んでいる。
所詮経済価値とは、その高低差が生み出すもので、格差の拡大は止められない。
貧乏人がいてこその金持ちであって、誰もが金持ちになれるはずがない。
だから、たとえ全国を東京にしても、何の解決にもならない。
ならば、全ての土地を経済価値で測るのでなく、もっと多様な価値観で土地利用をすべきではないだろうか。
・
みんなで地主とは、新しい土地利用の提案だ。
誰か一人が所有するのでなく、仲間がみんなで地主になる「民主化」だ。
地主の主は、主従の従でなく、主客の客でもない、当事者本人のこと。
主体的にその土地の魅力を高め、幸福を求め、収益も追及する人こそが地主だとおもう。
そして、「その人たちによる土地経営の仕組み」を民主国家と呼んでもいいのではないか。
それは日本から独立したいのでなく、日本が好きだからこそ主体的に小さな日本を作る取り組みだ。
そんな国づくりが、地域独自で自由に行われ、それが日本中に広がれば、この国は素敵な国になれると思う。
明治の初頭、全国に自活する集落が7万あったことを思い起こせば、合併を繰り返す役所は電子化・合理化をもっと進め、地方自治は「地主の仲間」で担えばいいと僕は思う。
